日本茶の代表的な品種
毎日飲んでいるお茶。どんな品種のお茶なんだろうか?と、ふと思ったことはありませんか?
日本で登録されている品種の数は、2020年の時点で120品種以上あります。

その中で一番多く栽培されているのが、よく耳にする『やぶ北』です。
国内生産の約75%はやぶ北です。やぶ北発祥の地である静岡では90%を占めています。
やぶ北の歴史
1908年静岡県でお茶を研究していた杉山彦三郎氏が竹藪を開拓し、集めたお茶の種で茶園を作り、その中の優秀なもの2本の内の一本が今のやぶ北の母樹。竹藪の北側に生えていたので、やぶ北と命名されたそうです。杉山氏の死後、1945年に静岡県の奨励品種に指定され、1953年に農林水産省の登録品種になりました。
母樹は現在静岡の天然記念物に指定されています。
やぶ北の特徴
綜合的に優れた品質で、煎茶・碾茶・玉露などあらゆる茶種に適正があり、とくに煎茶の品質は極めて優れています。旨味・渋味・苦味のバランスが良く、きれいな緑色が出やすいのも特徴です。
栽培地は、南は沖縄から。北は新潟までで、寒さに強く、凍害を受けにくいのが特性です。
育てやすく、品質も高く、根付きが良くたくさん収穫できることから、各地に広まりました。
お茶の品種と銘柄
品種とは、『やぶ北』『ゆたかみどり』『さえみどり』など。
銘柄とは、『静岡茶』『鹿児島茶』『宇治茶』など産地の名前をつけたお茶のことです。
同じ品種なのに味が違うのは?
お茶の味は、その土地の風土によってつくられています。生産農家の畑の育て方や栽培方法でもかわります。
静岡では露地栽培、鹿児島ではかぶせ栽培が多く取り入れられています。
120品種以上ある中で、2番目に多く生産されている品種は、ゆたかみどりです。
ゆたかみどりとは?
産地は主に鹿児島県です。
県内では30%近くを占める品種で、耐病性はあるが寒さに弱いため、九州の暖かい地域で栽培されています。
摘採期がやぶ北より一週間ほど早く、他の品種より早く全国に流通します。
ゆたかみどりの歴史
1966年に鹿児島県の奨励品種に登録されました。
鹿児島県のかぶせ栽培(被覆栽培)や温暖な気候にぴったりな品種だったため、現在30%近くを占めています。
ゆたかみどりの特徴
強い旨味を持ちながら、同時に渋味も強いゆたかみどりですが、被覆栽培により陽に当たる時間を少なくすることで渋味を抑え、深蒸しにすることでより渋味を抑えてマイルドなコクのある味わいを作り出すことが出来ます。
鹿児島のお茶の評価にも一役買っています。

菱和園ではやぶ北シリーズを各種取り揃えておりますので、ぜひお試しください。
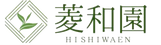
コメントを残す
コメントは承認され次第、表示されます。